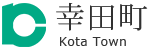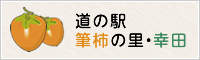本文
保険料
記事ID:0000472
更新日:2023年6月1日更新
令和6・7年度の保険料率
2年間の医療などの総額から、皆さんが病院などで支払う一部負担金や国・県・市町村からの負担金、現役世代からの支援金などを差し引いた額が、保険料の総額となります。この保険料の総額をもとに保険料率を決定しました。
| 令和6・7年度の保険料率 | |
|
所得割率 11.13% |
被保険者均等割額 53,438円 |
保険料の計算方法
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
|
保険料額(年額) 限度額80万円 |
= |
所得割額 賦課のもととなる所得金額※1(総所得金額等※2-基礎控除額※3)×所得割率11.13% |
+ |
均等割額 53,438円 |
※1 賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等(前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰り越し控除額は控除しません)
※2 総所得金額等=収入等-控除額(*)
*公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費等のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
保険料の軽減制度
低所得世帯の人には、保険料の軽減制度があります。
被保険者均等割額の軽減
世帯主とその世帯にいる被保険者の総所得金額等の合計に応じて、被保険者均等割額が次のとおり軽減されます。
|
軽減割合 |
対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
|---|---|
|
7割軽減 |
43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
|
5割軽減 |
43万円+(30.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
|
2割軽減 |
43万円+(56万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 |
※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適応されません。
※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。
なお、すべての元被扶養者の人に所得割を課しません。
保険料の減免制度
被保険者が、震災、風水害、火災などで著しく損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な方には、保険料を減免する制度があります。